梅雨は特殊な気候
- 雨が多い
- 気温が高い
- 湿度が高い
- 直射日光が強い
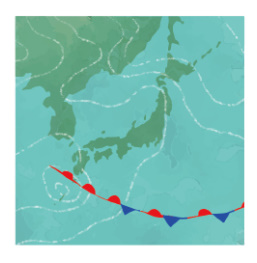 主に乾燥地帯に暮らしている多肉植物にとって、日本の梅雨時は苦手な季節です。「雨が多い」「気温が高い」「湿度が高い」そして6月の夏至は「直射日光が最も強い」また昼の長さも長いです。さらに日本では病害虫の発生もこの頃がピークで、冬型はもちろんのこと、比較的暑さに耐えられる夏型や春秋型にとっても、育てにくい季節になっています。
主に乾燥地帯に暮らしている多肉植物にとって、日本の梅雨時は苦手な季節です。「雨が多い」「気温が高い」「湿度が高い」そして6月の夏至は「直射日光が最も強い」また昼の長さも長いです。さらに日本では病害虫の発生もこの頃がピークで、冬型はもちろんのこと、比較的暑さに耐えられる夏型や春秋型にとっても、育てにくい季節になっています。
この時期は降雨量が多いです。雨の量のピークは地域によって異なり、九州・近畿・四国では6~7月に200~400ミリの雨が降ります。関東地域ではやや時期がずれ、7~8月に雨の量が多く東北地方や北海道は8~9月にピークを迎えます。
6~8月は一番気温が高く、西日本、東日本ともに8月にピークを迎えます。
雨が多く気温が高いと空気中に水分が残りやすく湿度がどうしても高くなってしまいます。
暑さのピークは7~8月ですが、太陽光の強さは夏至の6月付近が強いです。この時期は南中高度も高く真上から直射日光がかかるので、雨が多く曇りがちな気候からいきなり直射日光が当たると葉ヤケや溶けを起こしやすいです。
それではどんな点に注意して管理すると良いのでしょうか?
雨ざらしにしない
 外で栽培するならできるだけ雨ざらしにしないことが大切で、軒下やビニール温室など雨が当たらないところがベストです。しかし外で育てていると大雨で風が強く軒下まで吹き込んできたり、急な雨でビニール温室の窓を開けっ放しにしてしまうことも数回は経験します。
外で栽培するならできるだけ雨ざらしにしないことが大切で、軒下やビニール温室など雨が当たらないところがベストです。しかし外で育てていると大雨で風が強く軒下まで吹き込んできたり、急な雨でビニール温室の窓を開けっ放しにしてしまうことも数回は経験します。
普通の多肉植物であれば3日以上雨ざらしにしなければなんとかなることも多いですが、特別乾燥を好むタイプはしっかり雨よけしておきましょう。
水やりを減らす

湿度が高いと植物も蒸散量が減り、吸い上げる水の量も減ってきます。そんな梅雨時に春や秋と同じ分量と回数の水やりをしているとあっという間に過湿になり、根腐れを起こしてしまいます。
また湿度が高いと蒸れやすくなり、カビたり傷んだりするリスクも上がります。多肉植物の場合は普通の植物より乾燥気味にしないといけないので、表土が軽く濡れるくらいの量にとどめておいたほうが安全です。3日以上鉢の土が湿ったままになるのは水のやり過ぎのサインなので気をつけましょう。
通風を心がける
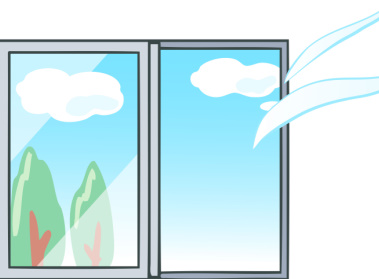 この時期水やり量と同じくらい大切なのが風通しです。室内は風通しが悪くなりがちでカビや病気が出やすく、閉めきった蒸し暑い部屋に多肉植物を長く置いておくと、溶ける(蒸れて枯れる)こともしばしばです。涼しい時間は窓を開けて空気が流れるようにしたり、扇風機を回したりする方もいるようです。
この時期水やり量と同じくらい大切なのが風通しです。室内は風通しが悪くなりがちでカビや病気が出やすく、閉めきった蒸し暑い部屋に多肉植物を長く置いておくと、溶ける(蒸れて枯れる)こともしばしばです。涼しい時間は窓を開けて空気が流れるようにしたり、扇風機を回したりする方もいるようです。
外で管理している場合も温室のビニールや遮光ネットなどで通気が悪くなっているので、特に過湿に弱いタイプは室内置きのものと同様、扇風機で風を送ってやることもあります。
晴れ間の強い直射日光に注意
 6月の夏至の付近は太陽の角度も高く一番日差しが強いです。梅雨時は雨が降り曇りの日も多く暗い時期ですが、晴れ間に真夏のような日差しが差し込むこともあります。梅雨時に曇りが多く多肉植物も徒長ぎみになっています。また人と同じように多肉植物も直射日光への慣れが必要で、いきなり強い日差しに当てると葉が焼けたりやや軟弱になった株にダメージを与えたりする心配があります。
6月の夏至の付近は太陽の角度も高く一番日差しが強いです。梅雨時は雨が降り曇りの日も多く暗い時期ですが、晴れ間に真夏のような日差しが差し込むこともあります。梅雨時に曇りが多く多肉植物も徒長ぎみになっています。また人と同じように多肉植物も直射日光への慣れが必要で、いきなり強い日差しに当てると葉が焼けたりやや軟弱になった株にダメージを与えたりする心配があります。
梅雨明けの最初は午前中だけ日が当たる所に置き、11:00~14:00の間は遮光するか木陰などに移動させたりします。数日から1週間程度で慣れていきます。
病害虫を予防する
 6~8月は湿気が多く、カビが原因で起こる病気が発生しがちです。病気はカビ、細菌、ウイルスが原因になりますが、その中でもカビが8~9割を占めています。カビ病を起こさないためには予防やこまめなチェックが大切です。
6~8月は湿気が多く、カビが原因で起こる病気が発生しがちです。病気はカビ、細菌、ウイルスが原因になりますが、その中でもカビが8~9割を占めています。カビ病を起こさないためには予防やこまめなチェックが大切です。
特にセダムのうどんこ病、クラッスラのさび病、軟腐病が起こりやすいです。
またカイガラムシ、アオムシ、カメムシ、アブラムシなど害虫被害も多い時期で、農薬や殺虫剤で予防したり駆除したりする作業が多くなります。